Sabae City Federation of Parent-Teacher Association
����24�N�x�@�I�]�s�o�s�`�A����HEADLINE
12��7���i���j���j�I�]�s�o�s�`�A����@12������J�Â���܂����B
�c���ɕt���܂��ẮA���N�x�̌o�ߕ�A���N�x�̉�\��ґI�o�Ɏ���܂ōs���A���^���A�����F���A����
������܂����B�����̍��e��ł́A�����̕��ɂ��o�Ȓ����A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�Ȃ��A���N�x��\��҂́A�{�N�x�s�o�A����@����P�T�@���i���z���w�Z�j���I�ǂ��A�I�o����A�����v��
���F����܂����B




11��25���i���j���j�s�o�A�q��Ĉψ���q��Č��C�u�q��ču����v���G�R�l�b�g�����ŊJ�Â���܂����B
�@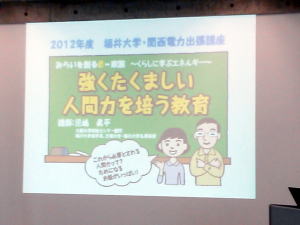



���j���̂�������Ƃ������ԑтł͂���܂������A�P�o�̗����l��
�i�q��Ĉψ����@���c�w���j
�@�@�@�@
11��11���i���j���j�u�s�o�A�\�t�g�o���[�{�[�����v���J�Â���܂����B
�@11��11���i���j���j�I�]�s�o�s�`�A�����Á@�u�s�o�A�\�t�g�o���[�{�[�����v���J�Â���܂���8:00�`12:30�����܂ŁA�_�����N�X�|�[�c�Z���^�[�ŁA�吨�̕��X�ɎQ�����Ē����A�M���������J��L�����܂����B
�Ȃ��A�e�R�[�g�D���́A�ȉ��̒ʂ�ł��B
| A�R�[�g | B�R�[�g | C�R�[�g | �c�R�[�g | �d�R�[�g |
| �I�]���w�Z | �䂽�����ǂ��� | �Џ㏬�w�Z | �g�쏬�w�Z | �I�]�����w�Z |


�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݖ{����A


�؉��P�o�x���ψ����@�^�c�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@


�I��鐾�@�g�쏬�w�Z�o�s�`��@����l�@�@�@�@�@�@�݂�Ȃŏ����^��






�u���j�����v�o��A�������q���r�b�N���I�@�@�@�@�@�`�R�[�g�@�D���@�I�]���w�Z�`�[��


�a�R�[�g�@�D���@�䂽�����ǂ����`�[���@�@�@�@�@�@�@�b�R�[�g�@�D���@�Џ㏬�w�Z�`�[��


D�R�[�g�@�D���@�g�쏬�w�Z�`�[���@�@�@�@�@�@�@�@�@�d�R�[�g�@�D���@�I�]�����w�Z�`�[��
�\�t�g�o���[�{�[�����F�l�̂����͂̂��ƁA�X���[�Y�ȉ^�c�Ŗ����ɏI���ł��܂������A�S���������
�\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�i�P�o�x���ψ���@�؉��K���Y�j
�@�@�@�@
10��17���i�ؗj���j��4����J�Â���܂����B
�@10��17���i�ؗj���j�I�]�s�o�s�`�A����@��4����J�Â���܂����u�J�v���W�F�N�g���ǂ��ӂꂠ�����Ɓv�̕��f���������Ă����Ē����܂����B
 �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@
�@�P��̃\�t�g�o���[�{�[���̑ΐ풊�I����s���܂����B�ΐ�͉��L�̒ʂ�ł��B
�R�[�g���̑ΐ�ŗD���������܂��B�P�K�̂Ȃ��l�Ɋ撣���Ă��������B�������Ȃǂ͂�����
| A�R�[�g | ���Z ���w�Z |
A-1 �I�]�� |
�`-2 ���z�� |
�`-3 ������ |
A-4 �O�썂 |
A-5 �I�]�� |
| B�R�[�g | �c�t�� | B-1 �I�]���c |
B-2 �䂽�� |
B-3 �I�]�c |
B-4 �_���c |
B-5 �i���c |
| C�R�[�g | ���w�Z�@ | C-1 �L�� |
C-2 �Џ㏬ |
C-3 �i���� |
C-4 �_���� |
|
| D�R�[�g | ���w�Z�A | D-1 ���H�� |
D-2 �ɉA�� |
D-3 �g�쏬 |
D-4 ���͏� |
|
| E�R�[�g | ���w�Z�B | E-1 �͘a�c�� |
E-2 �I�]���� |
E-3 �k���R�� |
E-4 ���ҏ� |
�@�I�]�s�o�s�`�A����@12��������L�̓����Ō��܂�܂����B�B
�����@12��7���i���j�@18:30�`
���@�x�m�����
10��1�Q��,13���@��68�C�k���u���b�NPTA�������x�R�����ɎQ������
�@�@��68�C�k���u���b�NPTA�������x�R�����ɎQ�����āi24.10.12�`13�j
�^�C�g�������������e�q�̂ӂꂠ���@�������ɘb����܂���ANKU��
�e�PP�̊����̔Y�݂͒P�N�̂��ߒ��������o���ɂ����APTA����̊Ԃɂ����x�������钆�A���̂悤�Ȗ����������邽�߂ɃX���[�K�����f���u�e�q�Ŏ��g�݁A�e�q�Ŋ������o����悤�Ɂv�ƁA�������e��M�S�ɐ��������g��ł��܂����B
�u�Ԃ����ς��v�́A�n��̃C�x���g�u�z�O��얼���}���\���v���̂���`���ŁA�Ԃ�e�q�ŐA���Đe�q�ň�āA�����i�[����������Ƃ������̂ł���B
�u�����������ς��v�́A�������̌����c�����āA�u���������l�v�ɂȂ�悤�ɂ������J�[�h���������ȂǍH�v���Â炵�čs���āA���A�̕��@���悸�͐e����q�ւ������̓������������Ă���ȂǁAPTA�Ƃ��Ēm�b���o�������A�͂����킹�Ď��g��ł����B
���k���̋K�͂͊W�Ȃ�PTA�Ƃ��Ă̑����̖��_���A���낢��Ȓm�b���o�������ė͂����킹�Ď��g�ނ��ƂŎq�ǂ������̐����̗ƂɂȂ�ƍl���A���̂悤�Ȏv�������L�������Ǝv���܂����B
�L�O�u���ł́u�s�ł���@�����k���v���M�����[�o���̋e�r�K�v�ٌ�m�ɂ��w�o��̐l������w���Ɓx�̍u�����܂����B
�v�w�ԁA�v�w�Ɛe�q�A�����ĎЉ�l�Ƃ��ẴR�~���j�P�[�V��������肭���邱�ƂŁA�ǂ��ΐl�W�����܂��B���̂����������u�������v�ł��B�u�������v�͊���݂Ėڂ��݂āA��Ɗ�������킹�Đ����o������R�~���j�P�[�V����������悤�ɂȂ�B
�e�Ƃ��č��厖�Ȃ��Ƃ͎����̌o���������邱�Ƃ͂ƂĂ��厖�ł����A����������t���邱�Ƃ��Ȃ��l�ɁA�e�����{���݂��Đe������Ă���p���������Ă������ƂŁA�q�ǂ������K���悤�ɂȂ�B�����Ď�������i��ŏo����悤�ɂȂ��Ă����܂��B
�Ⴆ�u�����Ȃ����v�ȂǓ����Ȃ��Ɍ����Ă������Ȃ��A����Ȃ��ƂȂ��������Ȃ��Ȃ�A�����Ă�����Ȃ��Ă��ꏏ�Ȃ猩����ăR�~���j�P�[�V����������l�Ȋ����ɂ��ė~�����ł��B
�Ⴆ�̘b�ŁA�X�|�[�c�N���u�̍��h�̌�̂����C�ɓ��鏀���̂��߂ɁA����O����ی�҂������S���̒��ւ��C��̒E�߂����ɓ���Ēu���Ă������ƂŒE�߂���������Ă��Ȃ��B�q�ǂ��̎����l���Ă̍s�ׂł����A���̍s�ׂ͑��̗��p�҂̎����l���Ă��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
��肷���邱�Ƃ͂��̐�q�ǂ��������������ɁA��l�Ƃ��Đ��n�ł���̂��A�����̍l�������Ă�̂��A��l�Ƃ��Ď������ēƗ����āA�������ĕv�w�̊Ԃł����̐l�̐l�i��������悤�Ȗ��͓I�ȑ�l�ɂȂ�邩�́A�q�ǂ������������B�̂�肽�����Ƃ��@���ā@�����ā@�y��������Ă݂ā@�����đ��肪�ڏ�ł��N��ł������Ɠ`���邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ��ė~�����B�����Ď����̍l�������������Ƃő�l����̗p���ꂽ��A�����̍l�������Ƃ͉��l�����邱�Ƃ�������A�ق��̎��ɂ���Ɏv���A�s�����Ƃ��o����悤�ɂȂ�B
�����̍l�������������Ƃő���̍l�������d���܂��B���̂悤�ȃR�~���j�P�[�V���������݂���厖�ɂ���悤�ɂȂ�܂��B
�w�Z�ł��ƒ�ł��w�b���E�����x�\�͂��ƂĂ���B�����̍l���������đ���̍l�������d����B�����Ă��̔\�͂��ǂ̂悤�ɂ��č��߂邱�Ƃ��o���邩���l���邱�ƁA�{�����Ƃ��厖�ł��B
���̂悤�ȋC�����ɂȂ�Ɓu�����߁v�͂Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B
TV�ł�������l�q�Ƃ͂ƂĂ��\�t�g�ŗD���������̘b�����ŋC���������₩�ɂȂ�܂����B
�搶�̂��b�̓��e���ꕔ�Љ�܂������A�����Ă���Ƃ��낢��ȏo�����܂��B����ȏo��͂܂����m��ʐl�Ƙb�����邱�Ƃ���n�܂�܂��B�b�����Ƃł��݂���������R�~���j�P�[�V����������l�ɂȂ�܂��B�����đ��d����C�������ӂ̋C���������܂�܂��B�e�q�ԁA�v�w�ԁA�搶�Ɛ��k�ԂȂǂ�������̊W�����������������Ǝv���܂��B
�Ō�ɂȂ�܂���������A�k���R���̈�ł���x�R�����ցA�������ɂ��ւ�炸
�i��ށ@����@��j
�X���Q���i���j���j�u���N���S�琬�I�]�s����c�v���J�Â���܂����B
�@9��2���i���j���j�I�]�s���z��قɂ�12:45���o�Ȃ��Ă��܂����B���H�����̕ł͐V���]�n��E�g��n����N�琬���c��� �̔��\������܂����B
�ǂ���̒n������W�I�̑���n��̓����������������Ƃ�����Ă��܂��B
�g��n��ł́A���N�琬���c��Ƒ����̑��̒c�̂����͂����Ƃ�����Ă��鎖����ۓI�ł����B
�u�n��̎q�ǂ������@�͒n��ň�Ă�v���̎��������������܂����B
�u����͊�x����搶�A���ҏ��w�Z�̐搶�ł��B
���b���́u�|�[�g�t�H���I�v
�m�[�g�Ɂu�����̖��v�u�����̍D���ȃg�R�v�u�F�B���猩�������g�R�v�Ȃǂ�Ԃ���̂炵���ł��B
������������g�߂ł킩��₷�������₷�������ł��B
�i��ށ@��@�ݖ{�����@�u���N���S�琬�I�]�s����c�v�ɎQ�����Ă��܂����B�j
 �@
�@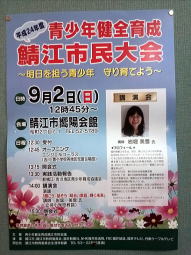
�@�@�@�@
8��20���i���j��)�u�����ߓ����s�����Ȃ����v���䌧�S�̉�c���J�Â���܂���
�t�F�j�b�N�X�v���U�@���z�[���u�����ߓ����s�����Ȃ����v���䌧�S�̉�c�ɏo�Ȃ��Ă��܂����B
���䌧���̏��w�Z�E���w�Z�E���Z�̍Z���搶��W�̐搶���ƕ��䌧�����w�ZPTA�A����E���䌧PTA�A����Ȃǎq��
���ɌW���F���W�܂�܂����B
���䌧���璡�`������ۂ̉ے����܂��A�����ߖ��s���ɑ��镶���Ȋw�Ȃ̎�g�݂̐���������܂����B
���䌧�ł́u�����߂̔F�m�����v�͌����Ă���Ƃ̎��ł��B
����̎�g�Ƃ���
�P�D�u�S�̋���v�̏[��
�P�D�����߂̓��̎�����⎖��W�̐���
�P�D�h�Ɠ��Ɋւ��W�@�ւƂ̘A���̐��̌���
�P�D�����ߓ����s���ɌW��鋦�c��⌤�C��̊J��
���̑� ���猻��̌����w�Z�⌧���w�Z�̍Z����̔��\������A�搶���̎�g�����������܂����B
���ł��A�������w�ZPTA�A��������̘b�͐g�߂Ɋ����鎖��Ƃ��� �A�搶���Ƃ͎��_���Ⴄ�b�ł����B
�q�ǂ��ɕ����Ȃ��搶��e�̗���Ƃ����ʒu�Ƃ��͋��������ǂ������ł��B
�i��ށ@��@�ݖ{�����@�u�����ߓ����s�����Ȃ����v���䌧�S�̉�c�ɎQ�����Ă��܂����B�j
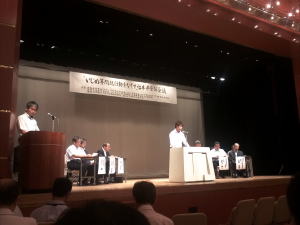
�@
8��4���i�y�j���j���䌧�o�s�`�A�����Áu�q��Č��C��v���J�Â���܂����B
�@�W���S���i�y�j���j�A���܂��Č|�p�قɂ����āA���䌧�o�s�`�A�����Á@�q��Č��C��ɎQ�����܂����B�ҁ[�Ղ�t�@���̎{�ݒ��@ �c�Ӌ`���@���ɂ��u����ŁA���C�̃e�[�}�́A�e�q�̃R�~���j�P�[�V�����ł����B
�@�R�~���j�P�[�V�����̑�1���́A�u���A�ƕԎ��v�������ł��B�v�t���̎q�ǂ��͌���������Ƃ�����܂����A���A�����킵�Ă���A����ȂɐS�z�͗v��Ȃ��Ƃ������b������܂����B���̃g�[���𖾂邭���C�ɂ��āA�e�̂ق����爥�A������Ɨǂ������ł��B
�@�܂��A�q�ǂ��Ɛڂ���Ƃ��ɁA�u�������ɂȂ邱�Ɓv��S�|����Ɨǂ������ł��B�b�̂�����܂炸�A�����̎�����Ȃ���������ƕ����ƁA�q�ǂ��̊��������Ă����܂��B
�@�v�t���́A�e�̉��l�ςƎq�ǂ��̉��l�ρi���f��j���Ⴄ���䂦�ɁA�䂪�݂����܂�邱�Ƃ�����܂��B�q�ǂ��́A�q�ǂ��Ȃ�ɐ^���ɍl���Ă���̂�����A�q�ǂ��̃y�[�X�ɍ��킹�Ă������Ƃ�����ƌ����܂����B�������A�e�̉��l�ς�������₷�����t�Ő������鎞�Ԃ���邱�Ƃ��K�v�������ł��B
�q�ǂ�����Ƃ��ɂ́A�������Z���p���Ǝ���B����Ŏ��邱�ƁA���̍s�ׂ��������邱�Ɠ��A��̓I�Ȏq�ǂ��ւ̐ڂ��������b����܂����B���[���A�̃Z���X�������Ď�������A�g�U���U�������������Ď�������A�q�ǂ���L������������ɂȂ�܂����B
�@�Ō�ɁA�u�ƒ�͗ǂ��q�����ꏊ�ł͂Ȃ��B�q�ǂ������ꏊ�v�Ƃ������t���A�ƂĂ��S�Ɏc��܂����B�ƒ�ł̃R�~���j�P�[�V������ʂ��āA�q�ǂ��̌���������A�B�ꂽ�˔\����������ł���悤�ɂȂ肽���ȁA�Ǝv���܂����B
�i��ށ@�q��Ĉψ����@���c�@���䌧�o�s�`�A�����Áu�q��Č��C��v�ɎQ�����Ă��܂����B�j

7��21���i�y�j���j��ʈ��S�X���w�����Z����ƁA���g���l�����������_�ōs�Ȃ��܂����B


�@�@�@�@
7��21���i�y�j���j�A���݂炢�فE�����ɂ����āA�Љ�𖾂邭�^���u�P�[�X������v�i�I�]�X���ی쏗����ɂ���Áj���J�Â���܂����B
�@�ŏ��ɁA�I�]�x�@���������S�ے��@�r�[�@�ꎁ�ɂ��u�b������A�����߁A��s�̑����A���̓����ɂ��Ă��b�����������܂����B��s�̏W�c���A�g�ѓd�b�ɂ���F�W�̊g�哙���A�ߔN�̔�s�̓����������ł��B�@��s��h�����߂ɂ́A�ƒ�ł̉�b�A�Y�݂��Ă����邱�Ƃ�����ƌ����܂����B�C�|����Ȃ��Ƃ�����A�������S�ۂ�T�|�[�g�Z���^�[�ɑ��k����Ƃ悢�����ł��B
�@�㔼�́A�u������������A�N�Ƃ��̕�e�v�Ƃ���������Ƃ����ăP�[�X���_���s���A������w�i�A�e�̂�����ɂ��āA�����Ȉӌ��������ł��܂����B�ĔƂ�h���AA�N�̗�������̂��߂ɂ́A��e���B�R�Ƃ����ԓx�����ׂ����A���������ɉ��E�ނׂ����A�Ƒ��Řb�������Ƃ悢�A�Ȃǂ̈ӌ�������܂����B����Z���^�[�A�e�n��̕ی�i�ɑ��k����Ƃ�����̓I�ȕ��@�������Ă��������܂����B
�Ō�ɁA�u�Љ�𖾂邭����^���v�Ƃ́A�ƍ߂��s�̖h�~�ƁA�߂�Ƃ����l�����̍X���ւ̗����A�ƍ߂��s�̂Ȃ����邢�Љ��z���S���I�ȉ^���ł��B���߂ĎQ�����܂������A�����Ƒ����̐l�ɂ��̉^����m���Ă��炤���Ƃ��厖���Ɗ����܂����B���Q���������������X�A���肪�Ƃ��������܂����B
�i��ށ@�q��Ĉψ����@���c�@�P�[�X������i��2��q��Ĉψ���j�ɎQ�����Ă��܂����B

�����Q�S�N�x ���䌧�c�E���E���o�s�`�����n��ʌ��C��@�O����
6��30���i�y�j13:30�`�@�z�O���������U�w�K�Z���^�[
�u����24�N�x�@���䌧�c�E���E���o�s�`�����n��ʌ��C��@�v���s���܂����B�m����w�@���� �@�x�] �a�� ���́u�H�ׂ�͂͐�����́@�h���A�Ȃ��H�炩�H�h�v�Ƒ肵�A�u�����s���܂����B
�吨�̊F�l�����������Ă��܂����B
�H��̍u���͔��ɈׂɂȂ�A�Q�����ꂽ�F�l�̐H��ւ̈ӎ������߂�f���炵���u���ł����B




���H���\�Z�Ƃ��ĉz�O�s�g�쏬�w�Z�Ɖz�O�s������ꒆ�w�Z���o�s�`��������܂����B
���̒P�ʂo�s�`������m�邱�Ƃ��ł��ǂ��@��ł����B�i��ށ@�L��ψ���@�[���j
�@�@�@�@�@
����24�N�x�@�I�]�s�o�s�`�A����@�q��Ĉψ���
5��25���i�y�j19:00�`�@
�u����24�N�x�@�I�]�sPTA�A����@�q��Ĉψ���v���s���܂����B��ς��Z�������A�e�PP����́A�����̎q��Ĉψ����ɂ��o�Ȓ����܂����B



�s�o�A�@�q��Ĉψ����@���c�w�����A���N�x�̕��j���̐����̌�A���ȏЉ�Ɏn�܂�A�e�P�o�q��Ĉψ����̍�N�x�܂ł̎��ƕ����Љ�Ē����A�F�l���������Ȃǘb�ɕ��������Ă���l�q�ł����B
�����܂��Ďs�o�A�@����@��؍��������A�q��Ăɂ������u�����̈ē��Љ�Ȃǂŕ�ƂȂ�܂����B
�����̂��o�ȗL��������܂����B
����24�N�x�@�I�]�s�o�s�`�A����@����
5��14���i���j19:00�`�@���@�I�]���N�����Z���^�[�i�A�C�A�C�I�]�j


�悸�́A����ɐ旧���܂��āA�{�N�x�@��@�ݖ{�������J��̈��A�������Ē����܂����B
�����܂��ẮA���o�̎I�]�s���@�q��S�j�l�@�I�]�s�c��c���@���������l�Ɍ䈥�A�����܂����B
 �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@ �@�@
�@�@�@�@�@�@
�c���ɂ��܂��ẮA�O�N�x�i23�N�x�j����n�܂�A�{�N�x��Ȃ�тɖ����Љ�A���ƌv��(�āj�A�\�Z�i�āj
�Ɏ���܂ŐT�d�R�c������������I�����邱�Ƃ��ł��܂����B�L��������܂����B
����23�N�x��@���{�G�������ޔC�̈��A�������܂����B1�N�ԑ�ς���J�l�ł����B

�I�]�sPTA�A����
��916-0024
���䌧�I�]�s����1����9-20
�I�]�s�������𗬃Z���^�[��
�I�]�s�o�s�`�A����@�L��ψ���